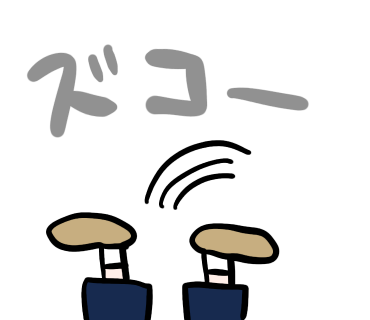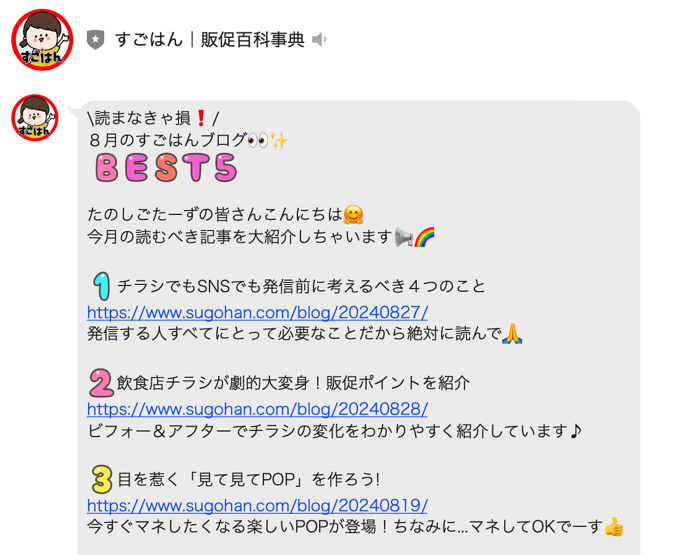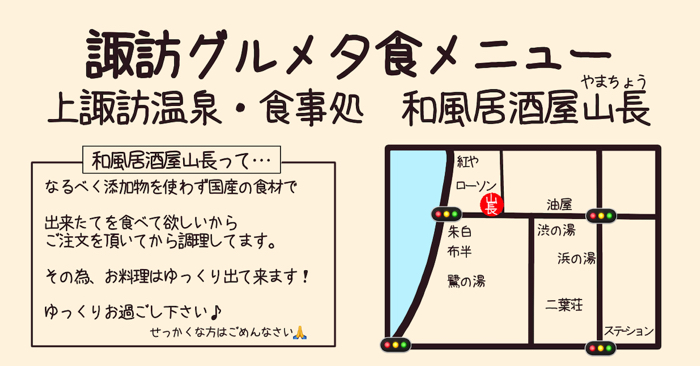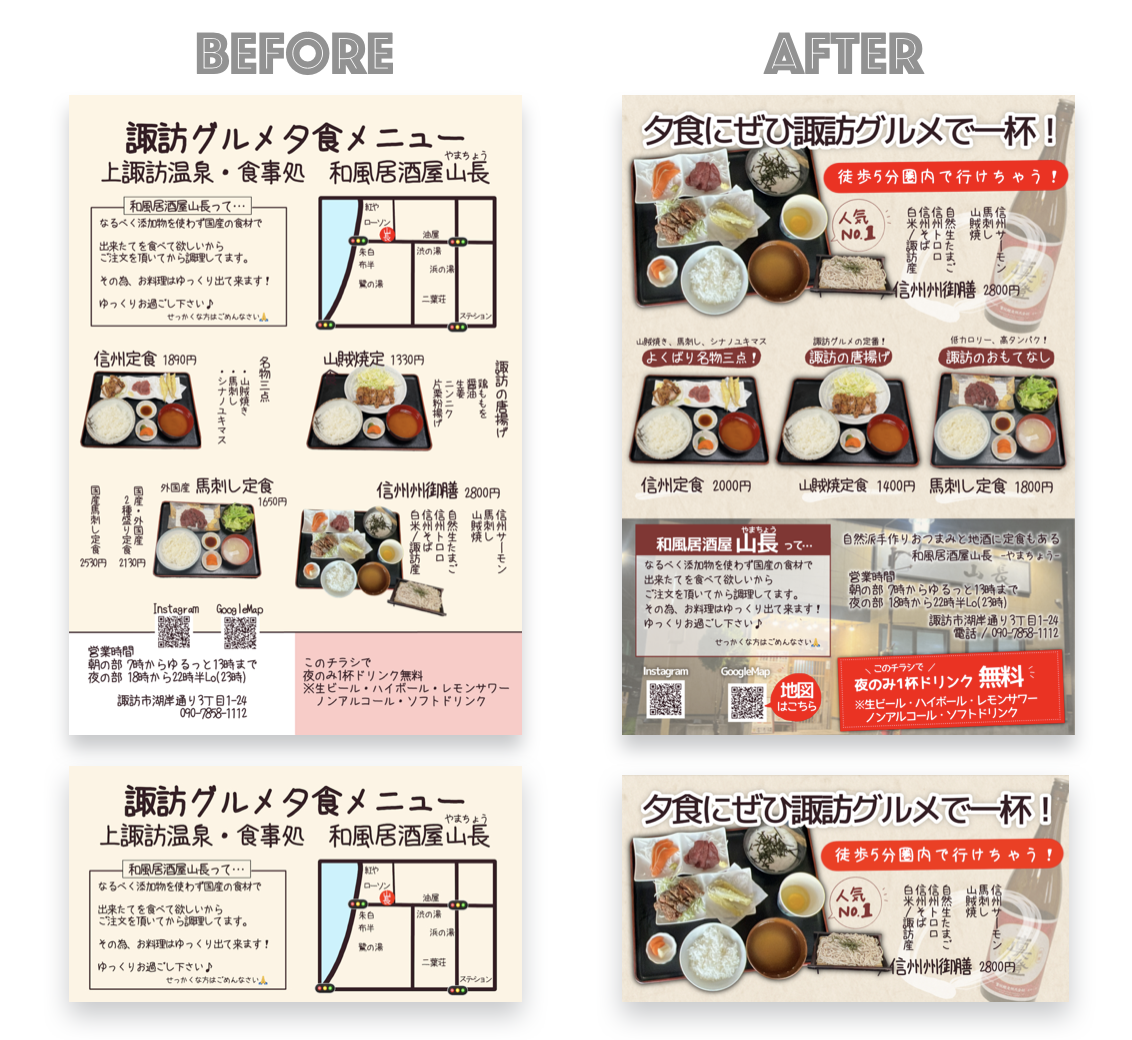キプロス出身のMちゃんがジムに通い始めた何ヶ月も前のこと。
Mちゃんから「食事前後の挨拶はなんて言うの?」聞かれたので「いただきます」「ごちそうさまでした」と言うんだよ、と答えました。
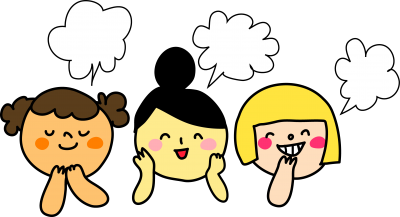
他にも「おねがいします」「おつかれさまでした」などいろんな日本の挨拶を紹介すると、「日本語って“ありがとう”の種類がたくさんあって素敵だね!」と言われ、ハッとしました。
英語だと「Thank you」の一言なのに、日本語にはその場ごとに感謝の表現方法があるんだ!
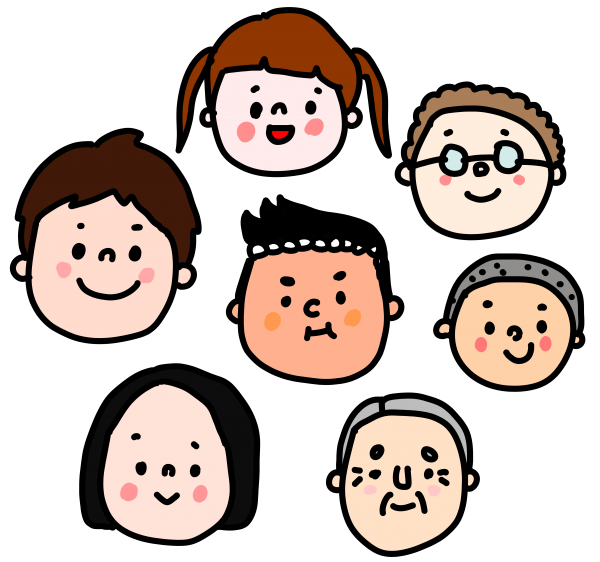
そうだよね。一つ一つ、感謝の言葉なんだよね。自分は言葉を発することで終わりになっていなかったかな。その言葉に感謝の気持ちを込めなくちゃね!
そんなMちゃんとの会話をよく思い出しては、日本語のやさしさや美しさを意識するようになりました。

他にも、日本語の擬態語や擬声語などの「どきどき、きらきら、さらさら、にこにこ、ゆらゆら」といった繰り返し言葉が可愛いそうです!これも確かに〜!
日本語をかなり覚えてきたMちゃんは、「イケてる男性を見たときは「おいしい」で合ってる?」と言うので、「NO!!」とみんなで爆笑!楽しい英会話の時間です!