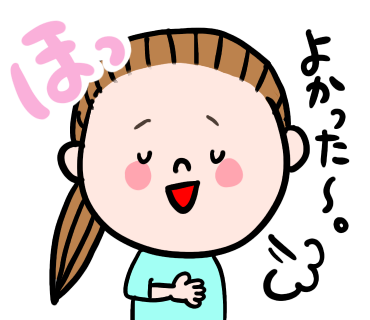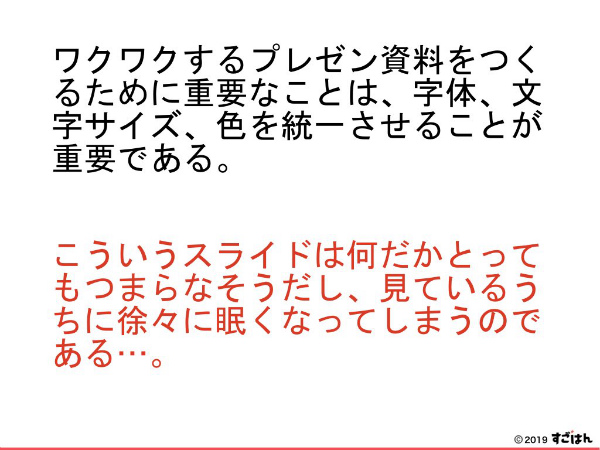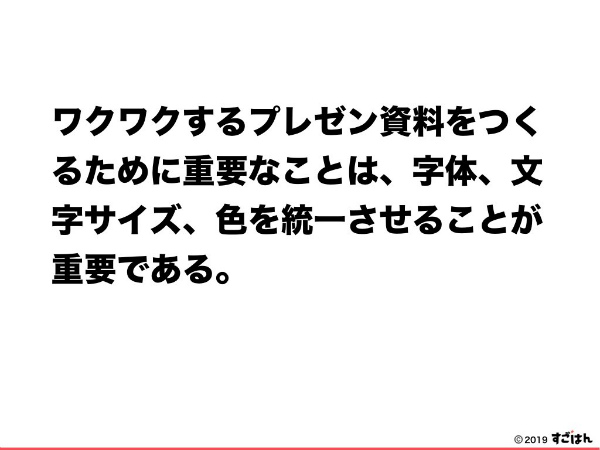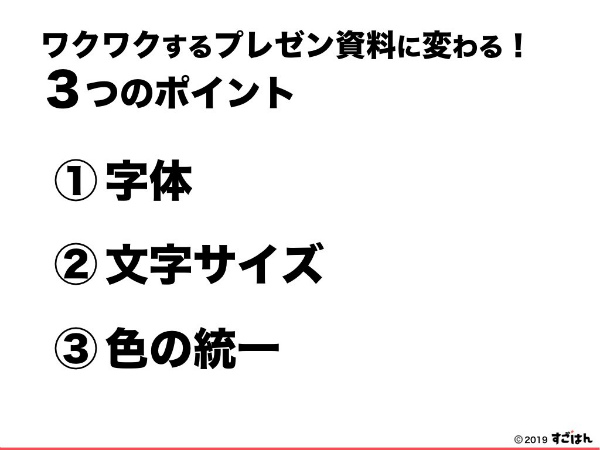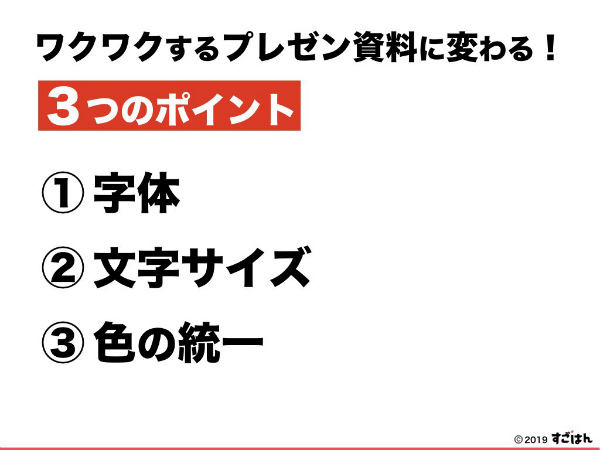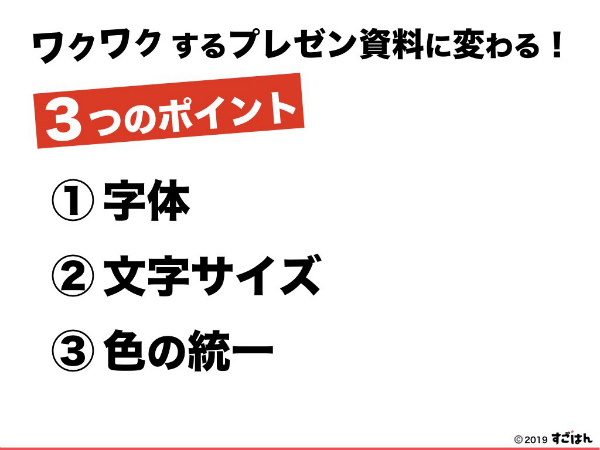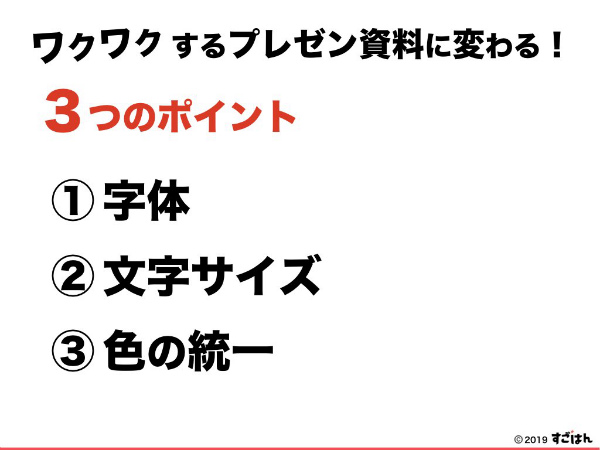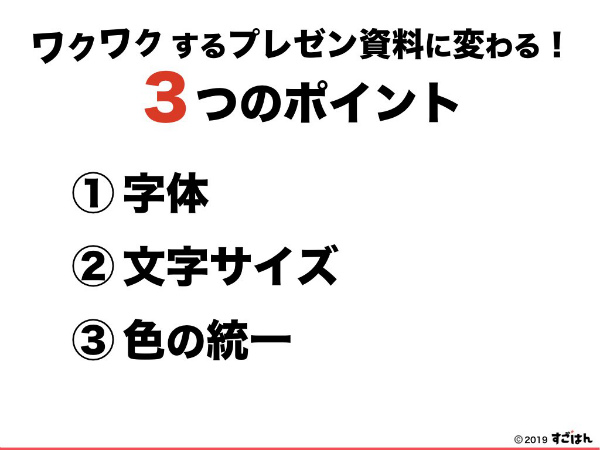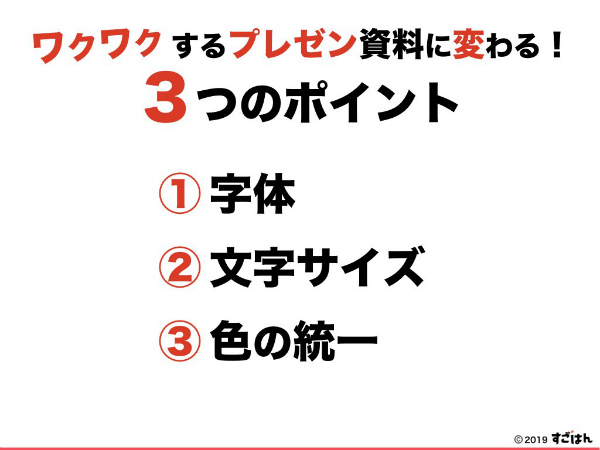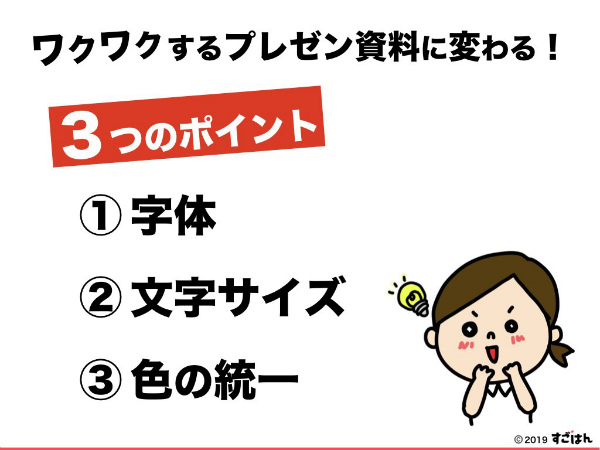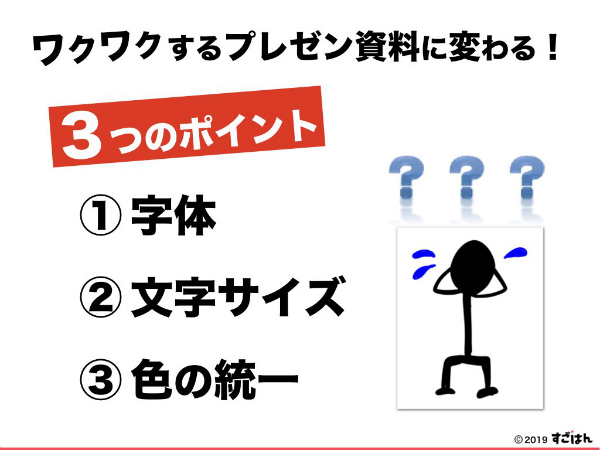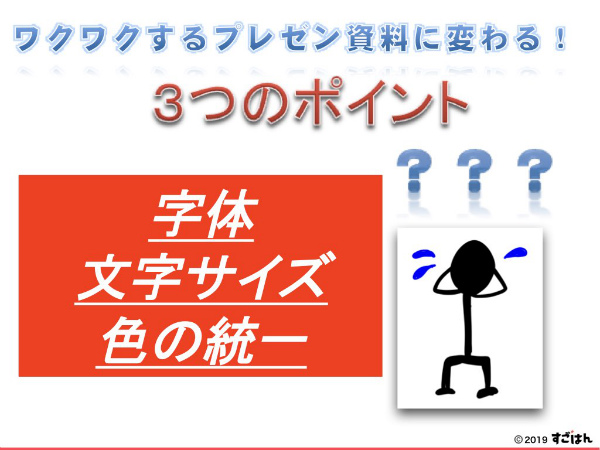「ブログネタがない!困った!」そんな時は、スマホやパソコン内の写真を見てみましょう。ブログネタが見つかることが多いですよ〜。
それでもダメなら「アクセス解析」をしましょう。Googleアナリティクスはもちろんもう登録していますよね!? まだの方は下の記事を!
で、アクセス解析をすると、どんなキーワードで検索されているか見ることができるので、チェックしてみましょう。

最近の私のブログでは「父の日」のPOPを検索してたどり着いている方が多いです。お店では、母の日が終わったら次は父の日の販促を考えますもんね〜。
人気記事TOP5の中にも2017年に投稿した父の日POPがランクインしています。
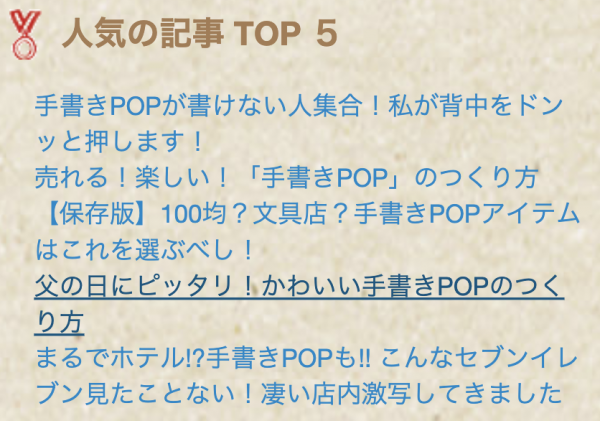
世間が知りたい情報がわかったところで、さっそく昨日のブログではこんな記事を書くことにしました。
父の日のPOPを書くということは、お父さんのイラストを描きたいと考える人も多いはず!と思ったんです。
それから、キーワード検索でたどり着いた記事からサイト内を行き来してもらえるように、2017年の父の日POPのブログ記事を編集して、2019年5月24日に書いたブログの記事のリンクを貼りました。
ブログネタは見つかるし、相手の欲しい情報を届けられるし、読まれている過去記事を活かすことができる!そして、読者さんを増やすきっかけにも繋がる!まさに一石四鳥〜!
ということで、必要とされる記事を届けるためにも、アクセス解析は定期的に行なっていきましょうね〜!