いろんな業界で活躍している人、目立っている人は、みんなブログを書き続けています。
目立っている人は、どかーんと花火を打ち上げているんじゃなくて、実は地味にコツコツやっているんです。
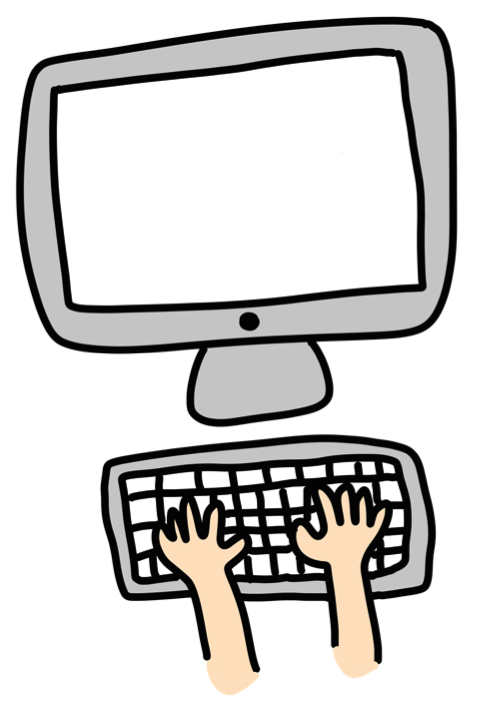
発信し続けなければ、すぐに忘れられてしまうし、知人からいいと噂を聞いてのぞいてみたサイトに動きがなかったら、せっかくの興味も冷めてしまいます。
いい仕事をしているなら、同じ熱量でブログで発信すること!
成田山新省寺のふくみさんも、ファッションプラザふじやの健ちゃんも、諏訪商工会議所の中沢さんも、エナジービジョンの奥山さんも、明和産業のエルサム事業部メンバーズも、コンビニアルバイターの中澤さんも、みんな毎日続けています!
「毎日はしんどいから、週三回でもいいかな?」と言う人は結局続かないパターンが多いです。休業日とかイベントとか、こちら都合のお知らせしか発信しなくなっていたりします。
私は忙しいときや海外旅行に行く時には、事前に数日分書き溜めて予約しておくんですが、毎日更新のペースが乱れると、「面倒臭い」っていう気持ちがどうしても出てきてしまいます。

だから色々考えずに、まずは毎日更新して習慣化した方が、逆に面倒臭くなく続けられますよ。
それから、あんまり気合いを入れすぎると疲れて継続できなくなるから、肩の力を入れすぎず、お客さんと会話しながら役立つ情報を伝えているような気持ちで、続けてみましょう!
続けた先に、「変化」をきっと感じられるはずです!!






